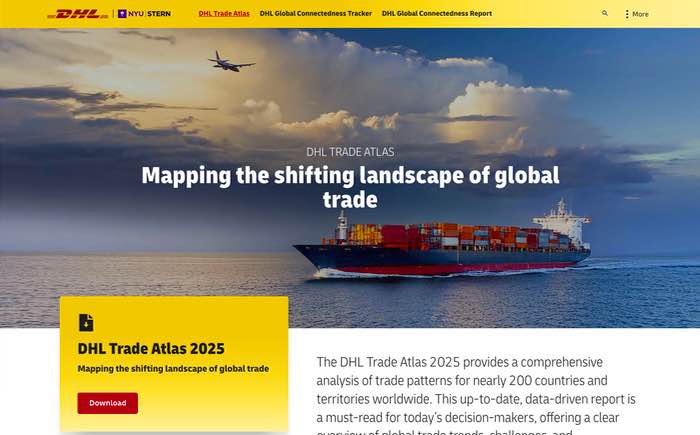
今後5年間、世界貿易は過去10年間を上回るペースで成長すると予測
DHLとニューヨーク大学スターンビジネススクールは3月12日( ボン/ニューヨーク発 )、「DHL Trade Atlas2025![]() 」を発表した。これは世界貿易での最重要トレンドを包括的に分析したもの。昨今、地政学的な緊張や関税引き上げの懸念が広がるなか、同レポートはデータに裏打ちされた国際的な貿易伸張の可能性を示している。
」を発表した。これは世界貿易での最重要トレンドを包括的に分析したもの。昨今、地政学的な緊張や関税引き上げの懸念が広がるなか、同レポートはデータに裏打ちされた国際的な貿易伸張の可能性を示している。
そんな「DHL Trade Atlas 2025」は、世界貿易とその見通しに関する豊富なデータに基づく知見と分析を特徴としており、同レポートはビジネスリーダー、政策立案者、教育者、学生、メディアを包括する様々なステークホルダーに向けて最新情報を提供するもの。
同関連サイトから閲覧できるインタラクティブ・コンテンツは、特定の国、地域、商品のカテゴリーごとに分析をカスタマイズし、貿易動向を調べることができる。データや画像をダウンロードするためのオプションも用意された。なお同レポートは、DHLの委託によりNYUスターンビジネススクールのスティーブンAアルトマン氏とキャロラインRバスティアン氏が執筆。2025年1月までのデータと予報を更新して、2025年2月に最終版を作成した。

その「DHL Trade Atlas 2025」によると昨年のトランプ米大統領の再選を受け、今後の貿易政策には不確実性が漂っている。しかし「DHL Trade Atlas 2025」では、世界貿易の成長が混乱に直面しても、驚くほど回復力を持つことを証明している。米国が関税引き上げ政策に着手しても、このパターンは継続する可能性が高いとした。
例えば最近の予測では、モノの貿易額は2024年から2029年まで年平均3.1%で成長すると予想されている。これはGDP成長率とほぼ一致しており、過去10年間と比較すると貿易成長が若干速まっていることを示している。これを踏まえると、米国の新政権が関税引き上げをすべて実施し、他国が報復措置を取ったとしても、世界貿易は今後5年間に亘ってゆるやかに成長することが判る。
こうした貿易拡大の可能性についてDHL Expressのジョン ピアソンCEOは、今年の「DHL Trade Atlas 2025は、非常に勇気づけられる貿易拡大を可能性を示しています。先進国であれ新興国であれ、貿易成長には依然として、大きな可能性があります。
世界貿易は、2008年の金融危機や新型コロナウイルス感染拡大、関税や地政学的な紛争など、考えうるあらゆる難題に国際貿易が耐え続けているのが印象的です。
今日のグローバルなビジネス環境に於いて、DHLはコストとリスクのバランスが取れたアプローチを確立することで、お客様のサプライチェーンを再評価し、効率性と安全性の両立を確実にすることができます」と述べた。

貿易成長における新たなリーダー:インド、ベトナム、インドネシア、フィリピン
また「DHL Trade Atlas 2025」で2024-2029年に掛けて、貿易増加のスピード(成長率)と規模(絶対額)の両方で上位30カ国に入る国は4カ国。それはインド、ベトナム、インドネシア、フィリピンと予測している。またインドは、中国(12%)、米国(10%)に次いで、貿易増加の絶対額が3番目に大きい国(追加的な世界貿易の6%)としても際立っているとした。
加えて貿易成長の絶対値が最も高い国々は、アジア、ヨーロッパ、北米としている。同時に、貿易の伸びが最も速いと予測される国には、アフリカやラテンアメリカの国が含まれる。
世界の主要地域別の分析で、貿易量の伸びが最も急速なのは、南・中央アジアサハラ以南のアフリカ、ASEAN諸国としており、その年平均成長率は5%から6%と予測した。その他の地域はすべて2%から4%の成長としている。
総じて顧客により近い場所で生産するニアショアリングへの関心が広がっている。しかしそれにも関わらず「DHL Trade Atlas 2025」では、貿易の地域化は進行していないとした。実際の貿易の流れは逆の傾向を示してるという。2024年1~9月期には、全貿易品目の平均輸送距離が過去最高の5,000キロメートルに達した一方で、主要地域内の貿易比率は51%と過去最低を記録した。

世界貿易が米国の政策転換にもかかわらず、楽観視できる理由とは
今年、最も注目される米国の政策転換について「DHL Trade Atlas 2025」では、米国の貿易政策がより強化されるにも関わらず、世界貿易の将来を楽観視できる理由がいくつかあるとし、引き続き、貿易を重要な経済機会として追求している国々のほとんどで米国との貿易障壁は、米国以外の国々同士の結びつきを強める可能性があるとした。
また、トランプ政権による関税の脅しの多くは、当初の提案とは異なる内容で決着したり、国内インフレの急上昇を防ぐために延期されたりする可能性もある。更に世界の輸入に占める米国の割合は現在13%、輸出に占める割合は9%で、米国の政策が他国に大きな影響を与えるには十分ではあるものの、世界貿易の将来を一方的に決定するほどではないとした。
これについてNYUスターン経営未来センターのDHL Initiative on Globalizationの上級研究員かつディレクターであるスティーブン アルトマン氏は、「世界貿易システムに対する脅威は深刻に受け止められなければなりませんが、世界貿易は経済や社会に大きな利益をもたらしていることから、大きな回復力を見せてきました。
米国は貿易から手を引くことは可能ですが、大きな犠牲を伴います。しかし、他の国々が米国に追随することはないでしょう。というのも貿易から手を引くことで、より深刻な影響を受けるのは小国だからです」と述べた。
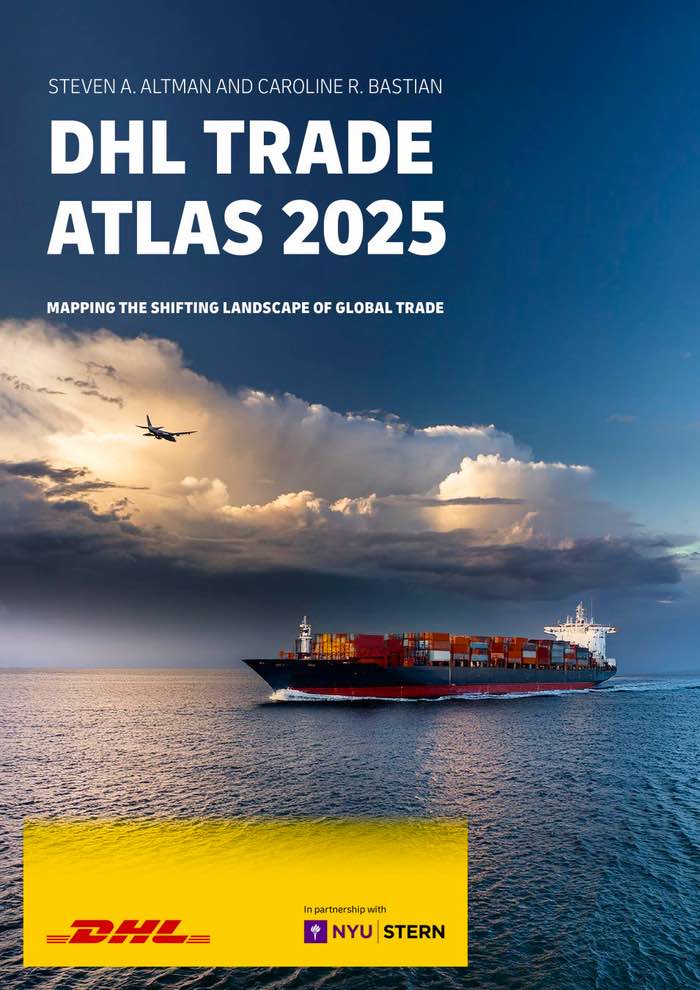 「DHL Trade Atlas 2025」10の主要なポイント
「DHL Trade Atlas 2025」10の主要なポイント
米中間の貿易割合は減少するが、中国製製品は米国への新たなルートを見い出す
「DHL Trade Atlas 2025」は、地政学的な要因による貿易パターンの変化に関する最新情報を提供している。米中と緊密な関係を持つ同盟国間の貿易は2022~2023年には、各ブロック内貿易と比較して減少したものの、こうした減少はわずかであり2024年には継続しなかった。
米中間の貿易割合は減少しているが、意味のある「デカップリング」を構成するほどではなかった。米中間の直接貿易は、2016年、世界貿易の3.5%から、2024年1~9月期には2.6%に減少した。
しかし、米国は依然として、中国からの輸入シェアを他の国々と同程度に維持している。また、米国の対中国輸入が過少報告されていることを示唆する証拠もある。さらに米国が他国から輸入している商品に中国からの輸入も考慮したデータからは、米国における中国製製品への依存度の有意な低下も見られないと結論づけている。
